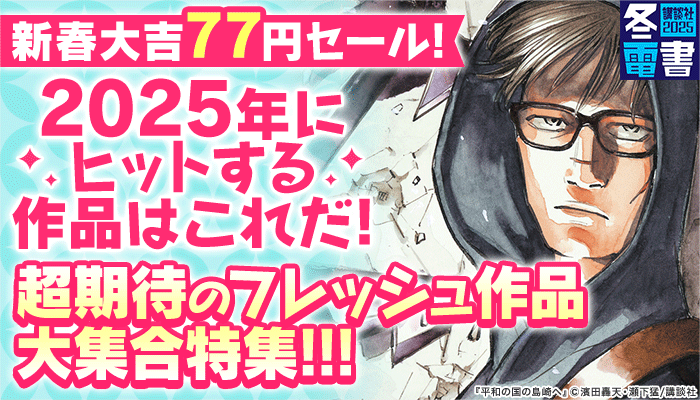普天間よ
著者 大城立裕 (著)
在日米軍基地の約75%が集中する沖縄。いまも「日常のなかにいつも戦争がある」基地のある町に暮らす祖母、父、娘、三世代それぞれの「普天間」。轟音の中での日常を切実に描き出す...
普天間よ
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
在日米軍基地の約75%が集中する沖縄。いまも「日常のなかにいつも戦争がある」基地のある町に暮らす祖母、父、娘、三世代それぞれの「普天間」。轟音の中での日常を切実に描き出す書下ろし中篇「普天間よ」を収録、戦前戦後を生き抜いて沖縄文学を牽引し続ける作家が沖縄の魂を織り込んで、「沖縄と戦争」をあぶりだす7篇。
著者紹介
大城立裕 (著)
- 略歴
- 1925年沖縄県生まれ。県立博物館長などを務める一方、創作を続け、「カクテル・パーティー」で沖縄初の芥川賞作家となる。ほかの著書に「花の幻」「真北風が吹けば」など。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
迂回しつつ書く沖縄問題
2011/08/29 12:30
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:24wacky - この投稿者のレビュー一覧を見る
芥川賞作家大城立裕の最新短編集は1993年発表の「夏草」から書き下ろしの「普天間よ」まで7作品が編まれている。出版社からの依頼で社会的注目度が集まる(っていた)「普天間飛行場移設問題」が題材に選ばれた「普天間よ」以外は沖縄戦が題材となっている。その構成により基地問題を中心とする現在の「沖縄問題」が、実は沖縄戦の歴史的記憶と切り離せないものであることを提示している。
「夏草」では、避難民の男の一人称が沖縄戦の現場を浮遊する「時間」を構築することに成功し、読む者の想像力を痛いまでに刺激する。その際に手榴弾を小道具として使う手腕が見事だ。《歩きながら、腰に当てた右手の手触りをたのしんでいた。》という「ことの途中」からいつのまにか虚構が始まっている書き出しは、「さっきから松原を通っているんだが、松原と云うものは絵で見たよりもよっぽど長いもんだ。」で始まる国民的作家の異色作をも想起させるほど、読み手を一気に惹きこむ。
「わたし」の語りは妻と二人で砲弾が飛び交う「今」を描写していく。もつれるような足取りで息絶え絶えの一人の兵隊が目の前で山羊を捕まえようとしている。死にそうになりながらなおも山羊を生け捕りにしようとする様をみて、「私」は滑稽に感じる。それは次の瞬間死ぬかも知れない自分たちの合わせ鏡にもなりうることを「私」は自覚し、しかしながらそれを「可笑しかった」という。語りの「私」はメタレベルから戦さを俯瞰している。
兵隊は間もなく息絶える。「私」は食糧を求め倒れ伏した兵隊の雑嚢の紐を解き、手榴弾をつかむ。ここから手榴弾をめぐる説話が展開される。そして一対の男と女を亀甲墓という死への欲動の場へと導く。二人がいざ「自決」せんとするその刹那、一匹のハブが現れ、二人は警戒して息を潜める。まさに死のうとしていた二人には思いがけず生への執着が残っていたのだ。その執着は次の瞬間、性の賛歌に転じ奔出する、手榴弾は妻の乳房に押し当てられ。
「普天間よ」は、「普天間問題」という短い言葉で斬り捨てられてはたまらない沖縄の根の深さを提示しようという明確な意図が読みとれる。普天間に生まれ育った主人公は新聞社の秘書をしている。彼女との関係性のなかで他の人物像が半ば寓意化されて描かれる。八十を越す祖母は普天間飛行場の土深く埋められたいわくつきの鼈甲の櫛を掘り出したいといい出す。市役所での押し問答での祖母の「両眼の強い光」に「私」は息を呑み、「この眼の色を見るためにこそ、この休暇を有り難く思ったのである」という。祖母の異様な執念を理解するには世代がかけ離れすぎていることを感じ距離をおきつつも、その眼の光に感応する「私」には、沖縄戦の継承の不/可能性が示唆されている。
つき合って一年が経過する平安名究は中部担当の新聞記者だ。ちょっとした問題を起こし北部へと左遷され、普天間から辺野古へと取材対象が変わる。基地反対運動の事務所に勤めている父は「あたかも右の耳でアメリカの飛行機の爆音を聞き、左の耳で復帰運動のシュプレヒコールを聞く」人生を歩んできた。しかし、運動の欺瞞に悩み突然蒸発する。
母親は琉球舞踊の師匠で、主人公とは母娘でありながら師弟関係でもある。米軍機の爆音が邪魔をし稽古が捗らないことの不平をこぼす「私」に、母親は仕方がないではないかとそっけない。ここで「私」が語る地の文がこうだ。
《いかにもあっさりとした諦めに似ているが、与えられた条件にどう忍従するか、または突破するか、だ。基地周辺に琉球舞踊道場が二十軒以上もあるが、その同じ条件のなかでの勝負さ、と言われたような気になった。
その話を父としたことがある。父は声に出さずに笑って言った。
「まあ、そういうことだろう。突破することと忍従することは、紙一重のようなものだからな」》
ここには基地反対か容認かという戦後沖縄の政治状況の分かり易い構図に組しない、少なくはない人々の思いがあるようだ、忍従のなかにも突破のエモーションがあるというように。問題はこのテーゼにリアリティがあるか否かだろう。それにしてはこの作品は、短編としての凝縮力がやや弱いのではないか。むしろ中篇規模の紙数のなかで、「突破」とは何かを書くべきではないか。それによって、突破と忍従の二項対立が渦巻きながら上昇し、説話構造が盛り上がっていく。そんな贅沢な作品を読んでみたい。