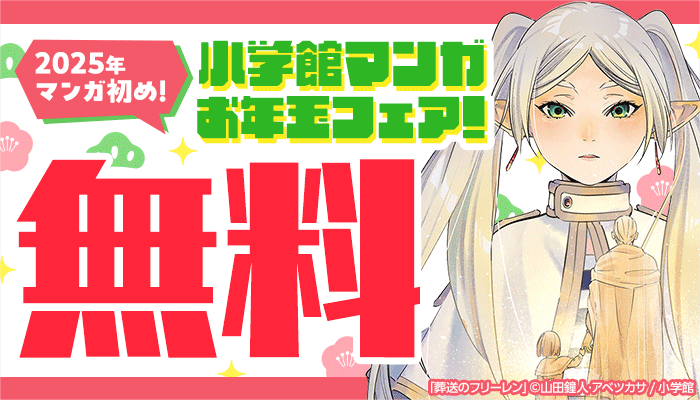悪ふざけか真面目なのか
2021/07/29 22:39
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ichikawan - この投稿者のレビュー一覧を見る
『HHhH』は歴史をめぐる生真面目ともいえるほどの真摯な小説であったが、ロラン・バルトをめぐるこの歴史改変小説は悪ふざけとさえ言いたくなるほどのスラップスティック的作品となっている。ここに作者の悪意を見るか、真摯さをみるかは様々であろうが、作者のあの時代のアカデミズムと政治への複雑な感情がそうさせたのだろう。
投稿元:
レビューを見る
Amazonはアメリカまで送れないって。なんでだろう? 英語で読むしかないのかな。今日、Amazonで注文できました。万歳。
読了。ま、なんということ! 哲学、記号学、言語学の有名どころがわんさか出てきて、訴えられないのかなあ、というレベルのことをやって、、、。本筋は推理小説、なんだろうね。面白かったよ。
投稿元:
レビューを見る
評を書くときには、読者がその本を読む気になるかどうかを決める際の利便を考慮し、どんなジャンルの本かをまず初めに伝えるようにしているのだが、本書についてはどう紹介したらいいのか正直なところ悩ましい。シャーロック・ホームズ張りの推理力を発揮する人物が、ワトソン役の警視とともに殺人事件の謎を追うのだから、謎解きミステリというのがいちばん相応しいのだろうけれど、ミステリとひとくくりにしてしまうと少々具合が悪いことになる。通常のミステリ・ファンが本書を面白がるとは思えないからだ。
『黒死館殺人事件』から法水麟太郎の超絶的な博学の披露を取り去ってしまったら、並みの推理小説と大して変わらないという評を読んだことがある。まあ、それは確かにそうだろう。衒学趣味(ペダントリー)を味わうことが謎解き興味より大事にされているのが明かな作品なのだ。名探偵を主人公に据えた探偵小説には、もともとそういうきらいがある。人の窺い知れない謎を解き明かすことのできる人物には、他を圧するだけの知の持ち主であることが要求されるのだ。それを出し惜しみするのはかえって無理がある。
シモン・エルゾグは、パリ第八大学(ヴァンセンヌ)で記号学の講座を受け持つ講師。今はサン=ドニにある大学がヴァンセンヌにあることから分かるように、時代は一九八〇年から八一年にかけて。フランスの政治で言えば、大統領がジスカール・デスタンからフランソワ・ミッテランにかわる激動の時代。社会党のミッテランが大統領に選ばれた日のパリの狂騒ぶりは、よく覚えている。
シモンが捜査に加わることになったのは、ジャック・バイヤール警視が大学を訪れ、無理矢理シモンを相棒に選んだからだ。ついには、一緒に大統領の執務室に招かれ、正式に国家に雇われることになる。どうやらことは国家的な一大事らしい。イデオロギー的にはヴァンセンヌに勤めるシモンは左派で、現大統領には批判的だが、ことの経緯上やむを得ない。何しろ、交通事故で入院中のロラン・バルトが、実は事故ではなく誰かに襲われた疑惑がある、というのだ。
この小説は、フランスの政権移行を背景に、時代の寵児であったロラン・バルトの事故死を題材にした謎解きミステリの形をとりながら、記号学や構造主義といった当時の知の体系を軽やかにさらってみせるとともに、フーコーやデリダ、ドゥルーズ、アルチュセール、ジュリア・クリステヴァ、フィリップ・ソレルスといった綺羅星のごとき哲学者や作家たちを巻き込んで、ロマン・ヤコブソンが残したとされる『一般言語学』の草稿をめぐる、てんやわんやを露悪的な形で嘲笑してのける、かなり厄介な小説である。
ただ、小説内に書かれているアルチュセールが妻を絞殺した事件は実際に一九八〇年に起きているし、ロラン・バルトが交通事故に遭ったのも同じ年の二月で、史実と創作を巧みにないまぜにしてみせる小説作法は、ゴンクール賞最優秀新人賞を受賞した『HHhH―プラハ、一九四二年』以来、この作家の得意とするところだ。本作の目玉は表題にある『言語の七番目の機能』である。ヤコブソンの本には言語の持つ六つの機能が紹介されているが、七番目はない。ところが、草稿にはそれが書かれていたというから穏やかでない。
バルトはどこからか草稿を入手し、ひそかに屋根裏部屋に隠し持っていた。そして、紙片の裏表にびっしり「言語の七番目の機能」について書き写したコピーを持ち歩いていた。何者かがそれを奪う目的で彼を襲ったと考えられる。アルジェリアで戦ったこともあるバイヤールは左翼とインテリには縁がない。コレージュ・ド・フランスを訪ねてフーコーにバルトの話を聞きに行ったのはいいが、話の内容がさっぱり分からない。そこで、話を翻訳してもらおうと記号学の専門家を探しに今度はヴァンセンヌを訪れ、シモンを見つけた次第。
風体が逞しく押し出しのいいバイヤールと線の細いインテリのシモンという、二人のコンビがなかなかいい。読者はバイヤール同様、記号学について何も知らなくても心配することはない。すべて、シモンが分かりやすく翻訳してくれる。そして、知的エリートの際限のない大言壮語を聞かされたり、性的に放埓の限りを尽くすさまを見せられたりするたびに、腹の中でバイヤールがつぶやく悪口雑言に共感する。この仕掛けが小説の工夫なのだ。
ビネは、フーコーやソレルスの文体を模倣して、パスティーシュの技量を見せつけながら、返す刀で、口舌の裏に隠された名誉欲やライヴァルの足を引っ張ろうとする敵愾心などをここぞとばかりに暴き立てる。言葉が華麗で文体が流麗であればあるほど、その内実の醜悪さが浮かび上がる。ミステリ仕立ての本作が意識したはずの『薔薇の名前』の作者、ボローニャの賢人ウンベルト・エーコを除いて、ほとんどのフランス人の哲学者や作家はひどい書かれようだ。フーコーの性豪振りなどあからさま過ぎて、これでよく文句が出なかったなと心配になるほど。
映画『ファイト・クラブ』から着想した「ロゴス・クラブ」という秘密の会合が面白い。拳ならぬ弁論で戦う一対一の争いである。弁論術のレベルによっていくつかの位階があり、相手を倒すことで位階が上がるシステムだ。もっとも、本戦ともなれば試合に敗れると指を切り落とされるという痛い判定が待ち受けている。まだ誰も知らない「言語の七番目の機能」を手に入れることができれば、恐らく無敵の勝者になれるだろう。
大は国家権力をめぐる暗闘から、小は個人の名誉欲まで、様々な思惑がいくつも重なりもつれあって何人もの人命が奪われる。パリ、ボローニャ、イサカ(アメリカ)、ヴェネツィア、ナポリと、大西洋を挟んでヨーロッパとアメリカを股にかけた壮大な謎解きミステリであり、スパイ小説でもある。カー・チェイスあり、傘に毒薬を仕込んだ暗殺あり、謎の日本人の二人組まで登場する一大エンターテインメント。時移れば、あの知の巨人もこう揶揄われるのか、と構造主義やポスト構造主義華やかなりし時代を知る者には、ほろ苦い思いを抱かせる問題作ではあるが、読ませる小説であることは間違いない。
投稿元:
レビューを見る
読むのに時間がかかった。軽やかにミステリーを楽しむという感じではなかった。出てくる登場人物について、この人どういう人だっけ?みたいなことをいちいち思い出したり調べたり。そんなことしなくても小説の中である程度説明してあるのだけれど。
投稿元:
レビューを見る
本書でコケにされているフランス現代思想のスターたちが綺羅星のごとく並んでいた時期に本を読み始めた私としては、文体模倣のところや何か、面白く読み始めることができたが、正直アクションもの、あるいはミステリーとしては展開は冗長かつ退屈で、露悪的にすぎると思われた。
投稿元:
レビューを見る
※私には難しすぎたので再読予定です。
大学講師のシモン・エルゾグは、哲学者、記号学者の
ロラン・バルトの交通事故死の解明のため
警視ジャック・バイヤールに無理やり駆り出される。
実際に起こった事件を元に実在の人物が
様々な事件を引き起こしていく。
学者には疎いのですがかなりめちゃくちゃな
書かれ方をしていて心配していたら、後書きでも
他の方の感想でも心配されていて笑ってしまいました。
言語の七番目の機能を得ることができたら
世界は良くなるかな?いや悪用されるだけでしょうね。
2020年11月16日再読
メモを取り、未知の人物名は検索しながら
読みました。
バルトが持っていた文書の行方、ロゴスクラブ
でのバトル、政治家たちの言動。
実在人物をこんなに書いちゃっていいのかと
やっぱり思うけど面白い~。
第1章のパリをしっかり読み込めばあとは
なんとか押さえ込む感じで読んでいけました。
シモンは七番目の機能を独力で手にすることが
できたのかどうか...。
筋をしっかり把握しながら読むと、ブルガリア人と
日本人が不気味。特にシモンを助けてくれる日本人は
結局なんだったのでしょうね。
本書を読んで実在人物をこれほどに書いても
誰も訴えない、というところがとてもフランス的
だと思いました。今、国内で、表現の自由で
揺れているのも頷けます。
※
ヤコブソンの言語の6つの機能
指示、感情表出、働きかけ、話しかけ
メタ言語的、詩的
ちょっとネタバレ的なので
下に書きます。
7つ目とされる機能
魔術的もしくは呪術的機能
投稿元:
レビューを見る
『「あなたたちフランス人はほんとに議論好きだから…」(You French people are so dialectical...)』―『第四部 ヴェネツィア』
もし記号論に興味があって、ウンベルト・エーコの「薔薇の名前」や「フーコーの振り子」や「プラハの墓地」は好きだけれど、ダン・ブラウンの「ダ・ヴィンチ・コード」はちょっとなあと思っていて、本棚にアラン・ソーカルとジャン・ブリクモンの「「知」の欺瞞」やスラヴォイ・ジジェクの「ラカンはこう読め!」があるなら、この本もきっと面白いと思うに違いない。何しろこの本は、実在の著名人たちを登場させてその相互関係を炙り出しつつ行われる痛烈な社会風刺であり、実際に起きた事故や事件に基づく幾つかの死を織り交ぜながら言語の七番目の機能という謎を巡る推理小説。冴えないパリ第8大学文化コミュニケーション学部の一講師が、BBC「Sherlock」のベネディクト・カンバーバッチのような洞察力を発揮しながら、ロラン・バルトの死に真に責任を持つ者を追いかけるという話なのだ。
鍵となる「言語の第七番目の機能」とは何を指すのかについては、もう一人の主人公であるフランス内務省情報局の一警視と件の大学講師の対話の中で説明が為されるのでロマン・ヤコブソンが何者であるかを知らなくとも構わない。だが、フランスの歴史(特に戦後)、文化、社会が背景として色濃く文脈に滲出して来るので、主要な人物の政治的立ち位置などを知らないと著者ローラン・ビネが何を当て擦りたいのかがよく判らなくなる。訳者あとがきにもあるように、この本は記号に溢れた本であるので、例えば「ミシェル・フーコー(=認識論の大家)」というような受験勉強的知識だけではなく「同性愛者、薬物常用者、共産党に入党するも後に離脱、但しルイ・アルチェセールとの親交は維持」などということも知ると、登場人物たちの相関図の見通しが利き易い。特に、フランスにおける左派と中道右派の対立、構造主義とポスト構造主義の対立などが一人ひとりの著名人の名前に結びつくと俄然面白さが倍増する。
『人生は小説ではない。少なくとも、あなたはそうであってほしいと思っているだろう』―『第一部 パリ』
そういう虚実ないまぜの小説の面白さとは別に、やはりこの本には言語の機能、記号論的な面白さが溢れているように思う。特に対話形式となっている文章には、構図によって読み手の側に作用するよう仕掛けられた記号が数多くあるように思う。そして、パリ、ヴェネチア、イサカなどの土地や登場する建物に込められた仕掛けなど。そこでいちいち立ち止まらずに読んでももちろん面白いが、「矢印」を意識して読むと本書は更に興味深いものとなるだろう(なのでネット環境のあるところで読むことをお勧めします)。また、ウンベルト・エーコがしばしば「劇中劇」ならぬ「物語中物語」の構図で、登場人物たちに対する作家(≒読者)のメタレベルの視点を無意識の内にずらすように操作しているのとは逆に、ローラン・ビネはしばしば作家として読者に話しかけることによって読者の視線をコントロールする。その物語の次元を逸脱する行為は徐々に登場人物にも波及し、主人公は自分が小説の中の登場人物であること��疑い始めるのだ。その時、この構図は読者を神の視点から引きずり下ろし、登場人物の視線を思わず避けたくなるような心理を生み出す。物語の中の言葉を借りるなら、「メタディスクール(言説についての言説)」の作用線の方向をひっくり返したような働き。それについて語っていた筈の言葉によって、語っていた者が作用を受ける。但し、それを「読む」時には「語っていた側」は必然的に「読む側」に置換される。このような一つ下位の次元から上位のメタレベルへの侵入という構図はミヒャエル・エンデの「はてしない物語」でも使われていたけれど、「物語の中の物語上の登場人物」→「物語の登場人物」というフィクショナルな関係を越えて、「作家」→「登場人物」→「読者」というリアルな関係になっているところが記号論的な働きを意識させるようで面白い。あるいはこれは言語の「呪術的機能」なのか、などと考えて見たりする。
言語の第七番目の機能について、物語の中でエーコが「魔術的機能」『ある発話が世界についての何かを明示するだけに留まらず、実現するかしないかはともかく、その発話を通じて、なんらかの行動を誘発しようとする』と語るところは意味深だ。単純に捉えるなら日本語の「言霊」という考え方に通じるものと片付けるところだが、ローラン・ビネがこの本を通して何かを誘発しようとしているのだとしたら、と深読みしてみても面白いのかも知れない。例えば、二人組の日本人のメタファーは現実の世界の何を譬えていて、どんな働きをすることを期待されているのか、とか。
投稿元:
レビューを見る
「HHhH」の著者の新刊ってところは気になりつつ、バルトだのフーコーだのの名前に怯えて手を出せてなかったのを遅ればせながら。
2回読んだけどやっぱり記号学だの現代思想だのはさっぱり。これはもちろん著者や訳者のせいではなくてこちらの知識読解力不足なんやけど。
それはそれとして、バディものの冒険活劇としてオモロい。そしてさっぱりの中で「結局現代思想界ではエーコ最強」ってことでええのかな?
投稿元:
レビューを見る
1980年の物語。その頃俺は高2か?17才。多感な時期なのにフランス大統領選挙なんか全く知らなかった。
ロランバルトの死から始まる物語。フーコー、デリダ、ラカン、アルチェシェール、ジルドゥールズ、ガタリなどなど綺羅星の如き面々。終いにはウンベルトエーコまで!そのころ全く知らなかった一時代を築いた思想家のオンパレード。興奮した。
四十過ぎて読んだ彼らはもう役目を終えたんだな。さぁ行こう!その先へヽ(^o^)丿
投稿元:
レビューを見る
哲学をちょっとかじっただけの私でも知っているような有名人が次々と!
登場人物がこれだから、読み始めたときはかなり難解に思えて、私はこの本を最後まで読めるのだろうか…と不安になった。
そんな思いも杞憂に終わり、物語が大きく動く100頁あたりからは、話のスジがわかりやすくなり、頁を繰る手も速くなっていった。
言語学、言論、アクション、エロ、複雑に絡まってゆく思惑、言語の七番目の機能という謎。
総頁数500弱と私にとってはなかなかの長編だけれど、刺激的な展開で最後まで飽きずに読み切ることができた。
爽快感のあるロゴスのやりとりはまさにファイトクラブさながら!
シモンの活躍ぶりは目を見張るばかりで、話が進むごとにひょろひょろの弱っちい印象が塗り替えられていった。
バイヤールも最初と随分印象がかわる。
この2人のドタバタっぷりがまた面白くて、もう一度2人に会いたい!と思わされる。
ただ、もう少し登場人物や時代背景に明るければもっと楽しむことができたのかもしれない。
また機会が巡ってきたら手に取ってみたいと思う。
投稿元:
レビューを見る
ローランビネ「言語の七番目の機能」tsogen.co.jp/np/isbn/978448… ロランバルト暗殺、という設定の一応ミステリ仕立てだけど登場人物は全員錚々たる実名でエピソードは虚実ない交ぜ、虚もいかにもありそうなものばかりでめちゃくちゃ面白かった。 作者はHHhHの人。ビネのメタのスタイルが好きだな(おわり
投稿元:
レビューを見る
主人公の二人以外は実在の人物で1980年代フランス他で実際の時間も織り交ぜながら「言語の七番目の機能」を探し求めるミステリー。
ミステリーと言いながら言語論であったりが入ってきて私には難解だった。
もっとこの時代の人物がわかっていればもう少し違ったか。
後半突然、シモンが弁論の達人になったり、「言語の七番目の機能」の行方だったり、ちょっと強引な感じも否めなかった。
皆さんの評価は高いが、私には難解すぎた。
投稿元:
レビューを見る
昔々、1990年代初めなのでこの小説の舞台となったときから10年後くらいにあたるだろうか、フランス現代思想なるものがエライと思って白さが眩しいみすず書房の本を色々と本棚に並べていた。それらの本の著者の中でも大物の一人であるロラン・バルトの死をめぐるミステリーで、フーコーやデリダも出てくると聞いて、これはいかにも読んでみなくてはと手に取った。
実在した思想家を登場させた荒唐無稽なパロディックミステリーなのだけれども、こいつはどれだけローラン・ビネが仕掛けたネタを見抜くことができるのか勝負を仕掛けられているのだ、と思った。ということで、いくつか仕掛らしきものを書き出してみた。そこには驚くべき時限爆弾も仕掛けられていたのだ。
以下、ネタバレ注意で。
---
・アルチュセールが妻のエレーヌを絞殺する原因となったエピソードは、ラカンの『エクリ』に収められた「『盗まれた手紙』についてのゼミナール」のパロディであることは明らか。絞殺したのは実際に起きたことなので、大胆だけど面白い趣向。こいつは比較的わかりやすい仕掛だ。
・BHL (ベルナール=アンリ・レヴィ)は1976年までミッテランのアドバイザーを務めていた。バルトの病室にソレルスとクリステヴァと共に現れたのは、彼がミッテラン側のスパイとして二人の行動を見張っていたから、と読むと合点がいく。
・2018年にクリステヴァがブルガリアの諜報機関に協力していたことが機密文書の情報公開で明らかになった。大した役に立たなかったという話だが。このスキャンダルが公になる前に書かれたこの小説の中でクリステヴァとブルガリア諜報機関がその関係を思わせぶりに出てくるのは先見の明というのか、そういう噂はもとより彼の国ではあったのか。クリステヴァの言い訳はブルガリアに残した家族に配慮したためということだが、本作中にクリステヴァから父への手紙が書かれていたのは偶然にしては驚き。現実も小説もどっちも奇なり、という珍しい例。時限爆弾一発目。
・ときおり小説内に「作者」が顔を出すのは、ロラン・バルトが宣言した「作者の死」への対抗なのだろうか。小説の技巧として成功しているとはあまり思えないが、それも含めての皮肉も込めた表現なのだろうか。『物語の構造分析』をもう一度読みなさいと言われているような気もする。
・デリダが死んだのは2004年。作中、おいおいここで殺しちゃうのかと思った。どこで生き返ってくるのかと思ってたら最後まで生き返らなかった。最後には物語の筋上死んでもらわないといけない事情があったのはわかったが。
・一方で自殺させられたジョン・サールもまだ存命。サール=デリダ論争の相手を殺しちゃったら、自殺しないといけなかったのかな。AIの議論で有名な中国語の部屋を論じた論文を出したのがちょうど1980年。というようなことを調べるためにwikipediaを見ていたら、2017年に84歳で24歳の助手にセクハラをしたかどで訴えられて2019年に大学を追放されている。現実の君が実は一番破廉恥だったかという意外なるオチが用意されていて素晴らしい。二発目の時限爆弾。
・デリダが偽の言語の七番目の機能を即��で作った、という設定は、ヴェネチアにおいてソレルスがロゴス・クラブで理解不能な弁論を行うことを通して、デリダのテクストへの痛烈な批判になっている、と言っていいはず。おそらくローラン・ビネはデリダのことが殺したいほど心底嫌いで、彼の熱心な読者ごと小馬鹿にしているのだろう。
・ソレルスが去勢されたのはバルトの著作『S/Z』の分析対象となった『サラジーヌ』の主人公が去勢された歌手であったこととも関連しているというのはこじつけか。いや、そう読むこともまた読者に委ねられているのだ。そもそもソレルスが自身の著作『女たち』でクリステヴァ、バルト、ラカン、アルチュセールなどの実在の人物に仮託した小説を書いているので、まだ存命だがこれくらいしても文句あるまいと思ったのだろうか。
・第五部パリの1981年5月の全仏オープンの決勝は、小説の通りボルグとレンドルでフルセットまでもつれたところまでは本当だが、最終的にはボルグが勝って、全仏4連覇、6度目の優勝を飾った。「自分が小説の登場人物ではなく、現実世界に生きている証拠がほしい」と思いながら見ていた全仏。敢えて現実と違う結果を書くことで現実ではないということを虚構である小説の中でも表現したということか。赤土のクレーコートのローラン・ギャロスとロラン・バルトのRolandが共通であることは偶然ではあるまい。ちなみにローラン・ビネは綴りが違う。残念。
・エピローグのナポリの地震の復興でカモッラというマフィアが多額の復興資金を着服した話は本当の話。ひどい話だ。
・分からないのは日本人二人組がなぜあんなに味方をしてくれるのか。バルトが日本びいきだったからかな。ちなみに第一部で日本料理について、箸は食べ物を虐待しない、とか、いつも食べる人の前で作られるのは敬っているものの死を人前にさらすことによって神性化する(ちなみに、すき焼きのこと)、は創作ではなく実際にバルトが『表徴の帝国』の中で真面目に語っている。おかしな話だ。
・ちなみに主がいなくなったバルトの部屋で置かれていたヤコブソン著『一般言語学』で、シモンも触れた「魔術的もしくは呪術的機能」について書かれているのは、第四部詩学、手元のみすず書房の第10刷でP.190である。確かにリトアニアのおまじないもロシア北部の呪文もある。これは嘘作り話ではなかった。疑ってすまない。きっと栞はこのページに挟まれていたんだな。自分もここに栞を挟んでおこう。
----
それにしてもつくづく、フランス現思想は言葉遊びが過ぎたものだと思った。でも、それがよいところでもある。
NHK 100分de名著 ブルデュー『ディスタンクシオン』でも次のようなエピソードが紹介されている。
「ジョン・サールが、フーコーに対してなぜあんなに難解な書き方をするのかと聞いたところ「フランスで認められるためには理解不能な部分が10%はなければならない」と答えたという。そのことを、さらにブルデューに話したところ、「10%はだめで、少なくともその二倍、20%は、理解不可能な部分がなければ」と語ったという」
この本を読むにあたって本棚から引っ張り出したバルトがやっぱりわからんなと思っていると、石川美子さんという方が『零度のエクリチュール』、『記号の帝国』(旧版『表徴の帝国』)、『ロラン・バルトによるロラン・バルト』(旧版『彼自身によるロラン・バルト』)といったところを訳し直していることに気が付いた。石川さんは、中公新書から『ロラン・バルト 言語を愛し恐れつづけた批評家』というロラン・バルトの紹介本を出しているようなので、まずこれを読んでみようかなと思ってkindle本をさっきポチってみた。わからなさを楽しむのがまた楽しみ。
投稿元:
レビューを見る
『HHhH』も十二分に変わっていたが、本作も振り切りっぷりは凄まじく、実在のフランス哲学界の大御所達をトンデモキャラとして描いていた。何人かはご存命な上に、作中で勝手に殺してしまった人もいるのだから、名誉毀損で訴訟沙汰にならなかったのかと勝手に心配になったが、これで文学賞も受賞したというのだから、フランス人の感性は解らない。
投稿元:
レビューを見る
『HHhH』がめちゃくちゃおもしろかったこともあり、同作者の続編はずっと気になっていた。明らかに難しそうなタイトルを見て距離を置いていたがついに読んだ。予感は正しく相当難解な部分もありつつ思った以上にエンタメにで驚いたし読みやすかった。改めて著者の筆力に感服した。とはいえ450ページ強で結構重たかったのは事実…
言語には六つの機能があることがヤコブセンにより提唱されているが、実は七つ目があり、その能力を使って世界をコントロールできるかもしれない。こういったマクガフィンが設定されており厨二病感も否めない中、哲学、言語学のエッセンスが大量に含まれているので読み進めるのが結構大変だった。特にこれらの学問に明るいわけでもないので、登場人物の背景を知らないことも多く戸惑った。ただ著者の特徴としては小難しさをエンタメで乗り越えさせてくれるところにある。サスペンスとして十分にオモシロく、特にメインの登場人物であるシモンとバイヤールのバディはいつまでも見ていたい、いい感じの凸凹具合で楽しかった。訳者あとがきで言及されていたが、2人のモデルはシャーロック・ホームズとジャック・バウアーらしい。怒涛の展開と場所の移動っぷりは確かにドラマ『24』そのものだし、学者的なアプローチで謎に迫っていくのはホームズそのもの。新旧二代サスペンスヒーローを使って描くのは哲学や言語学。。。無茶苦茶すぎ!さらに厨二病的な展開として『ファイト・クラブ』のディベートバージョンも用意されており後半は大きな鍵となってくる。さながらラップのフリースタイルバトル。設定は分かりやすいけども、そのディベートで議論されている内容は難しくて分かったような、分からないようなものもあった。ただ繰り返しになるが、スリリングな展開を生むのがうまいので読む手が止まらないようにはなっていた。
『HHhH』で見せた得意のメタ展開も健在しており、著者も登場するし、今回は主人公によるメタ構造の指摘もあって愉快だった。(『マトリックス』よろしく自分が現実にいるのかどうか?=小説の登場人物なのでは?という問い)また実在する or 実在した学者がたくさん登場するし、実際の事件をモチーフにしてサスペンスが展開していくのも前作同様。事件や出来事はそれぞれ点でしかないが、それを小説という線で繋いでいく手法は興味深かった。『HHhH』はナチスものなので理解できたけど、今回は実在した(実在する)学者たちをフィクションとしてエゲつない方法で死なせたり、傷つけたりしていて、さすが表現の自由が進んでいるフランスだなと感じた。