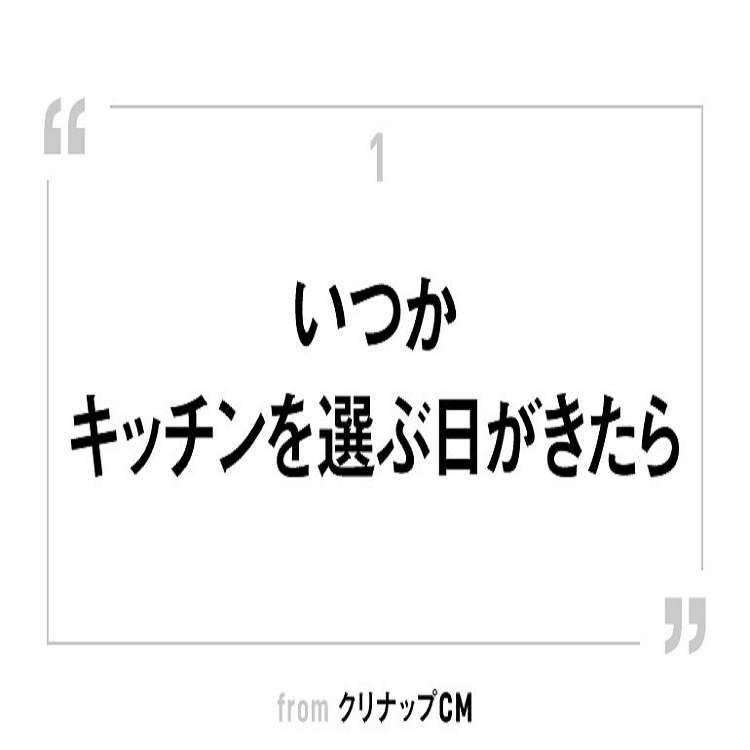「これ以上男らしく生きるのは無理」 コップの水があふれるように気持ちが限界を超えた


元画像:RichVintage / Getty Images
昔、たぶん五歳くらいの頃だと思うが、父に歩き方を直されたことがある。当時のぼくの歩き方は、足のつま先が内側に入っていたので、父が「それじゃなよなよして見える、男の子ならもっと外側に開いて歩け」と注意してきたのだ。指導員となった父の横で、自然と内側に入ってしまう自分のつま先を、意識して外に向けながら歩いたことを今でもよく覚えている。
とはいえ、直されたことについては、何の感情も持っていない。実際そのときも「そういうものか」と素直に従った記憶があるし、のちのち違和感を覚えて元に戻したりもしなかった。ただ、今の自分がその出来事を振り返ってどう感じるかと言われたら、そこには父の、自覚すらしていない偏見がうかがえるというか、彼は息子のぼくに男らしい人間になってほしかったんだなとは思う。
男らしさというのは奇妙なものだ。ぼく自身、特に好んで意識してきたわけではないのに、いつのまにかそういうものを気にする男性になってしまっている。男は人前で泣かない、弱音や愚痴を吐かないなどの「やってはいけないこと」はもちろん、仕事ができる、運転がうまい、スポーツが得意など、「世の中の人が男性に期待すること」に至るまで、どこかで自分がそういった条件をクリアしなければいけないような気がしてしまう。
“男らしさ”を意識するあまり自然体でいられなくなる
今はもうぼくも年齢を重ねて、無理なものは無理と割り切りがつくようにもなってきたが、身の丈を知らない若い頃は、自分の力量以上の「男性」になろうとして、無理をしてしまっていた。
中でも、恋愛感情の絡む女性に対する振る舞いは、その最たるものだった。付き合う/付き合わないに関係なく、ぼくは好意を持っている女性の前では、なんだかんだ男らしくありたい気持ちが強かった。だからなるべく明るく振る舞い、自分の悩みを話さなかった。頭の中にごちゃごちゃと面倒くさい思考や感情が渦巻いてしまうタイプの人間なのに、相手に好かれたいがために、いつも平然としている男を演じていた。
もちろん恋愛なのだから、ある程度相手にいい顔をしてしまうのは仕方のないことではある。ただ、ぼくの場合は、そうして本心を明かさないことが、相手の女性に対して壁を作ることにつながってしまっていた。
たとえば、ぼくは自分が我慢すれば済むことなら、「いいよ」とあっさり引き受けてしまうところがあった。旅行の計画や、車の送り迎えなど、相手の女性が「こういうことを望んでいるんだろうな」というのが見えると、それをしようとしてしまう。でも、面倒なことを引き受けたことに対するマイナスの感情にふたをするため、結果的に相手の女性と過ごす時間を、少しずつ自分にとって苦痛なものに変えていた。
男らしさの押しつけにノーを突きつけたい
我ながら面倒くさい男だったと思う。実際、ぼく自身も、ずっと息苦しさを感じてはいた。でも当時は、その気遣いをどうしてもやめることができなかったのだ。それどころか、そういうプレッシャーを重荷に感じていることすら言語化することができなかった。ぼくは女性の願望を察して動くのがいい男だと思い込んでいた。そして自分で自分の首を絞めながら、その両手を首から引きはがす方法がわからなかった。
そんなわけで、ぼくは自分のせいであまり幸せな恋愛をしてこなかったのだが、三十歳を過ぎた頃に、「いい加減、もうやめよう」という気持ちが湧いてきた。特に明確なきっかけがあったわけではなく、コップの水があふれるみたいに、これ以上は無理だと思ったのだ。

Combomambo / Getty Images
こんなふうに自分じゃない自分を演じていても到底幸せになんかなれない。世の中には、社会が押しつけている女らしさに「ノー」と言って生きている女性が増えてきているのだから、同じように男らしさに対してだってノーを突きつけてもいいはずだ。
それ以来、ぼくは意識して男らしさと距離を取るようにした。世の中で、なんとなく男性がすることだと思われていたり、それをすることで印象がよくなったりするようなことでも、したくないときはしたくないとはっきり言うようになったのだ。旅行の計画もしないし、車の運転もしない。たとえ男としてそれはどうなのと首をかしげられようとも、心がちょっとでもしんどいと感じる行為は避け、自然体でいられることを重視した。
思いのほかすんなりと考え方をシフトすることができたのは、ちょうどその頃に結婚したのも大きかったと思う。一般的に結婚というのは、家庭内で役割分担を強いられることから、男らしさや女らしさをさらに強めるようなところがあるが、ぼくと妻は、お互いにその形を望まなかった。男だから稼がなければいけない、女だから家事や育児をしなければいけないというようなことはなく、二人で助け合ってうまく家庭が回るなら、「らしさ」なんてどうだっていい、という考えで暮らすことにしたのだ。
おかげで、家の中にいる限り、あの息苦しさとストレスを生む「男だから/女だからこれをやるのは当然」というような空気はない。できないことや苦手なことを許されながら、そのままの自分で日常を過ごせるのは、お互いにすごく快適だった。
ただ、一歩でも家の外に出ると、家庭内と同じように生活するわけにはいかなくなる。特に男らしさや女らしさをもとに振る舞うのが当然だと思っている(というより、存在すら意識していない)人に会うと、直接会話をしなくても、一緒の空間にいるだけで疲れてしまう。
そんなときは、とりあえずひとつは居場所があるのだからいいじゃないか、と自分に言い聞かせはするのだが、やはり疲れるものは疲れるのだ。だから、声には出さないけれど、カナダのトルドー首相に倣って、その人に向かって「2018年ですよ」と心の中で言うようにしている。
BOOK
『たてがみを捨てたライオンたち』集英社/1600円(税別) 白岩玄 著

モテないアイドルオタクの25歳公務員、妻のキャリアを前に専業主夫になるべきか悩む30歳出版社社員、離婚して孤独をもてあます35歳広告マン。いつのまにか「大人の男」になってしまった3人は、弱音も吐けない日々を過ごし、モヤモヤが大きくなるばかり。 幸せに生きるために、はたして男の「たてがみ」は必要か? “男のプライド”の新しいかたちを探る、問いかけの物語。