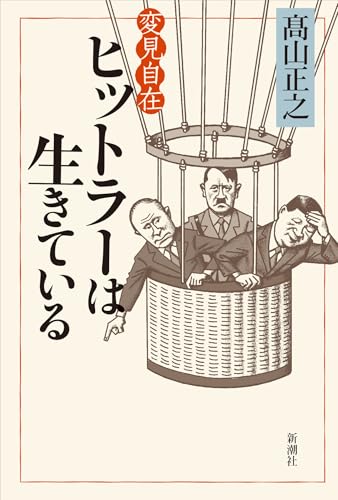すべてが齟齬した、としか言いようがない。
「一年前携へて来た三百羽の軍用鳩は本年一月から三回も実戦に応用して居るがシベリアは鷹が多いので折角通信の為めに放った鳩は途中で鷹に捕はれて了ふ」
上の記録は大正九年、ウラジオ派遣軍野戦交通部附として彼の地に在った長谷川鉦吉騎兵少佐の筆による。
一事が万事、シベリア出兵というものを、よく象徴した景色であろう。
(Wikipediaより、ウラジオ派遣軍司令部)
最初っから最後まで、とかく目算違いの連続、何もかもが噛み合わず、得たのは負債と傷ばかり。しっちゃかめっちゃか、血が血を招く無辺際の闘争の渦に絡め取られて沈み込み、足抜けさえもままならなくなったのが、すなわち
皇軍史上、おそらく最大レベルの汚点。拭おうにも拭いきれない失敗の
ところがだ。かくも愚劣で無謀極まる火遊びというか冒険を、いざ発動に至るまで推して推して推しまくり、力いっぱい熱狂的に推奨した者がいる。
ご存じ当時のマスメディア、──新聞各社なのである。

(飛騨高山レトロミュージアムにて撮影)
おまけに彼らはその熱狂を、自分の脳から絞り出したのですらない。
すべて、外部から植え付けられた。
具体的に言うならば、ブレスト=リトフスク条約の締結により、これまで東部に張り付いていた独軍が西部戦線へ殺到すると予測し、且つ焦慮した、英仏以下連合諸国のプロパガンダによって、であった。
『デイリー・メール』や『ロンドン・タイムズ』が口を揃えて「日本のシベリア出兵はもはや時代の必然」と煽り立ててやったなら、彼らはたちまち満月の夜の人狼みたく

(『サイバーパンク2077』より)
わけても『万朝報』の筆鋒たるや凄まじく、
「…露国兵が悉く日本兵に向って来ても、敢て恐るる所は無い、曾てロマノフ朝廷の為めに戦うたる時代の勇敢なる彼等さへも、我が兵には勝てなかった、況や彼等は今や闘志の無い者ではないか、無政府党の非戦論者が、誰れの為めに其の貴重なる生命を捧げる乎、シベリアへ派出したる我が日本兵が無人の野を往くが如くに進み得て、到る処の住民が箪食壺漿して、我が日章旗を歓迎することは明白なることだ。…(中略)…真に君国の事を思ひ、世界の大局に通じ、日本百年の長計を考ふる者は、誰れでも皆出兵に異議はないのだ」
一字一句が今にも火を噴きだしそうな、異常な熱に満ちていた。
帝国主義的口吻に希望的観測を厚塗りしたものであり、猛悪極まる組み合わせといってよく、一読するだに胸がむかつき、悪酔いの症状を自覚せずにはいられない。陸軍の機関紙でももうちょっと表現を抑えるのではあるまいか。結局この連中は、「日比谷焼き討ち事件」から何一つとして学ばなかったし、反省もしなかったのだろう。

かくて大日本帝国は涙の谷へと行進す。ああ、無情。
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。
この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。
↓ ↓ ↓
![]()