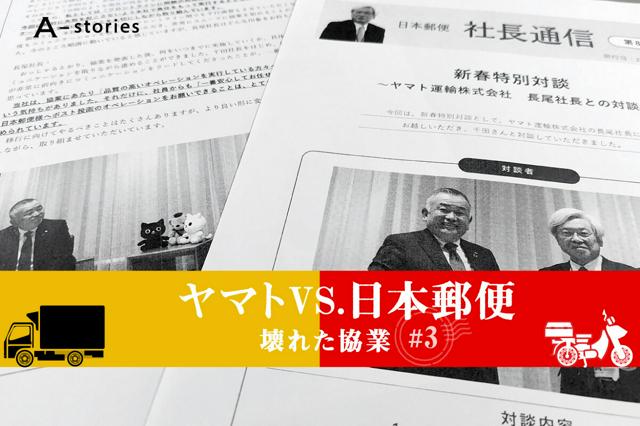「数字に一喜一憂せず、正しく恐れて」 地震研究者が橋本市で講演
地震の発生確率といった数字に一喜一憂せず、正しく恐れて日ごろからの備えを――。茨城県つくば市にある国の機関「防災科学技術研究所」で地震津波発生基礎研究部門長を務める汐見勝彦さんが15日、和歌山県橋本市で「南海トラフ地震って何だろう?」と題して講演し、約100人の聴衆にメッセージを発した。
「地震が少ないと思われている近畿地方だが、実は活断層がたくさんある。そのうち大きな地震が起きる」。滋賀県出身の汐見さんが冒頭で引用したのは、高校時代の地学教師の、こんな発言だった。この言葉に感化され、地震研究を志したという。
阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震は、内陸の活断層で発生した地震だった。橋本市など紀北地方を通る日本最大級の「中央構造線断層帯」を震源とするマグニチュード(M)8の地震が発生した場合、橋本市で震度6弱~7の強い揺れや紀の川沿いの低地での液状化が予測される。さらに、大阪府には「上町断層帯」、大阪府と奈良県の境には「生駒断層帯」があるという。
本題は南海トラフ地震。フィリピン海プレートが西南日本の下に沈み込むことで引き起こされたと考えられる大地震について、684年までさかのぼる世界でもまれな歴史資料が残っていることを紹介した。室町時代以降の発生間隔は90~150年で、1944年の昭和東南海地震・46年の昭和南海地震から約80年が経過している、といったデータを挙げた。
政府の地震調査委員会は今年1月、長期評価による地震発生確率値の更新を発表。南海トラフ地震については「今後30年以内の発生確率は70~80%」とした。汐見さんは「確率の数字は一つの目安に過ぎず、誤差もある。数字の変化に一喜一憂する必要はない」と指摘した。
県が2014年に公表した南海トラフ地震の被害想定では、建物被害の予測で橋本市の全壊率は2%と低いが、注目すべき点は半壊率10%の方だという。「半壊でも倒れた家具の下敷きになって亡くなる危険がある。大きな家具は壁にボルトで固定する、たんすは寝室には置かない、といった事前の対策が必要だ」と注意を促した。
今年8月8日、日向灘を震源とする地震の発生を受けて、気象庁が初の「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表した。世界でM8以上の地震103例中、7日以内に周辺でM8級の地震が発生したケースは7例だけだが、東日本大震災ではM7・3の地震の2日後に本震が起きており、その教訓を生かす取り組みとして臨時情報を出す仕組みが始まったという。
今回の臨時情報をめぐっては、海水浴場の閉鎖やJR特急の運休といった対応は妥当だったのかどうか、議論を呼んだ。汐見さんは内閣府・気象庁が19年に出したリーフレットを示し、「巨大地震注意の臨時情報を受けて特別に何かしてください、とは書かれていない。日ごろからの地震への備えを再確認するきっかけとして活用してほしい」と呼びかけた。