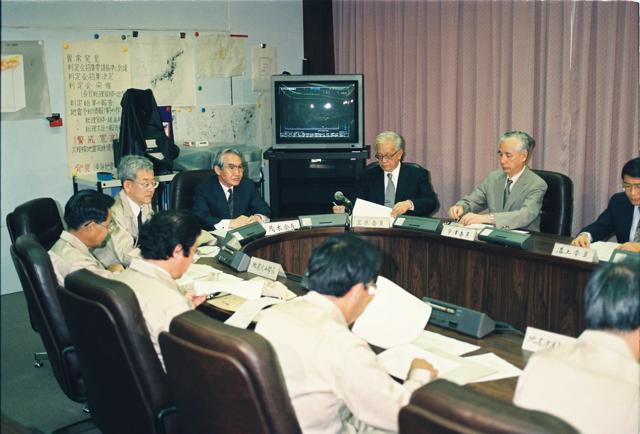第5回高速635メートル横倒し、「安全神話」砕く 被災構造物は伝える
「地震は海外とか遠くで起こるもの、という思い込み」
阪神・淡路大震災のちょうど1年前、1994年1月17日、マグニチュード(M)6.6の地震が米カリフォルニア州を襲った。高速道路のあちらこちらで、橋脚が壊れたり、橋桁が橋脚からはずれて落ちたりした。それでも当時、国や研究者は「日本の高速道路は大丈夫」と考え、「関東大震災並みでは破壊されない」などと説明していた。
だが、阪神大震災でもカリフォルニアと同様の甚大な被害が出た。神戸市内の高速道路では、橋脚と橋桁が一体化した「ピルツ構造」の区間で、635メートルにわたり横倒しになった。古い構造物を中心に、設計の想定を大きく超える揺れによる被害だった。
阪神高速道路(大阪市)の2年目の社員だった糸川智章・神戸建設部長(56)は震災直後に横倒しになった高架橋を見た。「想像を絶する光景に頭が真っ白になった」と話す。
入社3年目の伊藤学・技術部長(57)も、「高速道路が壊れるのは全く想像していなかった」と振り返る。同社神戸管理部(神戸市)で工事の積算、審査業務を担っていた。「地震は海外とか遠くで起こるもの、という根拠のない思い込みがありました」
伊藤さんは午前5時47分、大阪市内の自宅で大きな揺れを感じ、目覚めた。勤務先に向かい車を走らせると、至るところで橋桁と橋脚の間に使われる部品が落ちていた。午後1時前に職場にたどり着き、高速道路を歩いて調査した。
阪神高速は、大阪市と神戸市を結ぶ3号神戸線を中心に大きな被害を受けた。神戸線では4カ所で落橋し、943のコンクリート橋脚のうち、およそ4分の1が撤去、造り替えが必要なレベルだった。
他にも、鋼製の橋脚が途中の部分で空き缶をつぶしたように壊れたり、鋼製の橋桁の底に穴が開いたり。それでも、予定より早く翌96年9月には全線で復旧した。
同社は、これらの被災構造物34点を震災資料保管庫(神戸市)に展示している。99年に保管庫を開設し、2009年にはリニューアル。年間約2千人が見学する。伊藤さんは「自然は人知を超える。想定を超えることが起こり得ることを頭の片隅に置いてほしい」と話す。
時代による耐震基準の違いと耐震補強
阪神大震災では時代による耐震基準の違いが、被害の差となってあらわれた。
神戸線は66年から81年にかけて開通。連続的に壊れた区間などでは、鉄筋コンクリートの柱は、コストを抑えるために柱の上部で鉄筋を減らす設計をしていた。鉄筋の量が変わる境界で大きく変形し、コンクリートがひび割れ、鉄筋も破断した。
関東大震災(23年)を受け、世界初の橋の耐震基準が内務省土木試験所長によってまとめられたのは26年。その後、構造物の重さの0.2倍の地震力(水平方向)の想定が標準とされた。「震度法」という考え方の設計だ。
70年代、構造物の強度を上回る地震に対しても、コンクリートのひびや、鉄筋が伸びる「ねばり」で、倒壊を防げるとわかった。震度法に上乗せして、最終的な強度をはっきりさせる設計が世界の潮流になった。
しかし、日本では導入が遅れ…