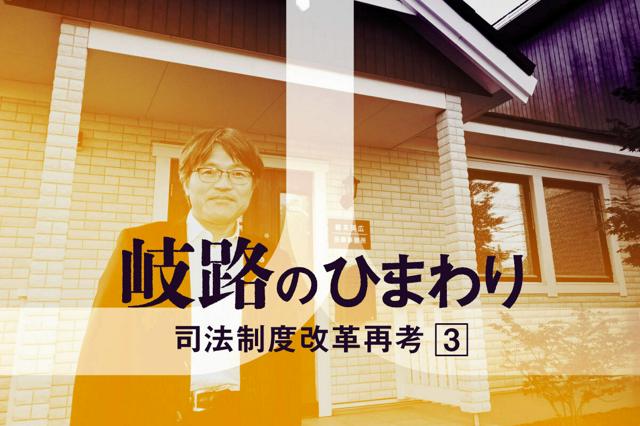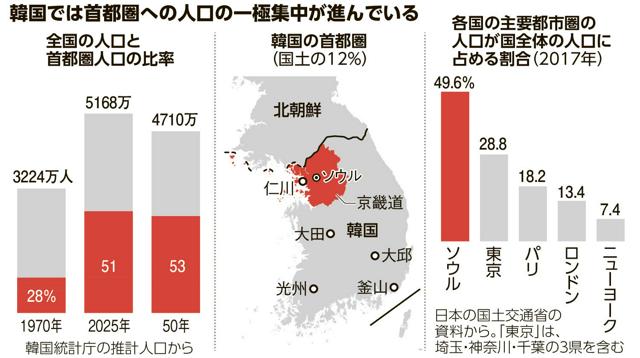「合格発表前」に決まる大手法律事務所への道 受験者にも「変化」
弁護士1人の存在が、司法へのアクセスを大きく左右する地域がある一方、国内には、500人超の弁護士を抱える「5大法律事務所」もある。
日本弁護士連合会によると、国内最多の西村あさひ法律事務所(東京)には2023年3月時点で650人の弁護士数が所属している。一つの法律事務所だけで、広島弁護士会(628人)を超える規模だ。
ほか四つの法律事務所も東京に本拠を構え、532~567人の弁護士を擁する。国内外を舞台に、主に企業合併・買収(M&A)や国際取引などの企業法務を扱う。集団で業務にあたり、迅速な解決をめざす。弁護士が働いた分だけ費用を請求する「タイムチャージ」が一般的だ。新人弁護士の採用人数は年間、数十人規模にのぼる。中には、全国各地に事務所を構え、地方の案件を積極的に引き受ける事務所もある。
ひまわりが表すのは「正義と自由」
司法過疎や複雑化する人権課題などを解決するため、法曹人口の拡大を目指した司法制度改革から約20年。ひまわりのバッジをつけた弁護士の数は都市部を中心に増えたが、地方では「弁護士が足りない」との声があがる。人工知能(AI)の進化や、裁判手続きのデジタル化に伴い、弁護士の役割も問い直されている。岐路に立つ「ひまわり」の今を追う。
法律事務所の採用活動について、明確なルールはない。だが、日本弁護士連合会は毎年、全国の弁護士会に対し、地方での就職の機会を確保するために、採用活動は司法試験の合格発表後に行うよう協力を要請している。5大法律事務所など大手事務所を中心に、合格発表前に「内定」を出すケースが少なくないためだ。
都内の法科大学院に通う井上貴尋さん(22)は24年8月、「5大」の大手法律事務所から「内定」の連絡を受けた。司法試験の合格発表は11月。3カ月も前のことだった。
周りには、春ごろには内定を得ていた同級生や、25年7月に試験を受ける予定の後輩で、24年末に内定を得た学生もいるという。
かつては法曹の実務を学ぶ「司法修習」で配属された地域を気に入り、その地で弁護士登録する人もいたが「『5大』と同じ企業法務を主戦場とする事務所は、採用活動を前倒しにしている。受験生の側も、周りがみんな内定をとる中、自分がとっていないと不安になる」という。
弁護士白書によると、50人…