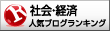(習作小品ホラー) 【猛暑の夏に凍死した男】
男は繊細に過ぎたのかも知れなかった。
男は精神を病んで入院していた。
痩せぎすで背のヒョロッとした男。
不安そうで神経質な表情は彼の消耗した心を表していた。
病院から出てきたのはごく最近のことだ。
ベッドが足りなくなり症状が落ち着いたということで男は退院しなければならなかった。
ツテを頼り、男はやっと貧相なアパートに落ち着いた。
症状が和らいだとはいえ、彼の神経は過敏なままだった。
病んで以来、彼は他人の話し声にひどく影響を受けるようになっていた。
人の言葉や声、他人の気持ちに影響を受けて体調が変化してしまうのだ。
この夏、暑いと人から聞けば極端に暑く感じた。
今日は涼しい、と聞けばとたんに真夏でも寒気がした。
自分は寒いのか暑いのか、気温に関係なく人の声に体が反応してしまうのだ。
それは自分独自の感覚がないようなものだった。
彼はとてつもない不安感に襲われた。自分を失う恐怖を彼は感じた。
街中で誰かの「咳が出そう」なんて声を聞く。
そんな声を聞くだけで彼は激しく咳き込んでしまった。
咳がしたいわけでもないのに、風邪でもないのに、人のそんな話し声を聞いただけでどうしても咳き込みが止まらなくなってしまった。
激しい咳にたまりかねて彼は病院に行った。
検査しても何も異常はない。
「気のせいだよ。あまり考えないことだ。」
「気候病というのではないですか?」
「そんな病気などありゃせんよ。」
医者はそう言ったが彼自身には思い当たるものがあった。
他人が感じたこと、他人が言った言葉に体が反応してしまうのだ。
「気候変動」などと口々に人が言うからだ。
意識の側から感じ方を変えられてしまうのだ。
「あー、疲れた。」
そんな呟きを聞いても同じだった。
いきなり眩暈さえ襲ってきたものだ。
道端にフラフラと彼は倒れ込んだ。
男は他人の感覚にひどく影響されやすくなっていた。
体調が悪いはずはない。
食事には気をつけているし睡眠は取っている。
しかし人の声が、人々の呟きが耳に入ると彼は自分をなくしてしまった。
まるで感覚を奪われるように他人の意識が彼を覆った。
「臭ぁあーーい」なんて、そんな声を聞いたとたん、猛烈な臭気を感じていきなり嘔吐してしまった。
そんなことはしばしばだった。
人の感覚がまるで自分に乗り移ってくるかのようだった。
「暑い、暑い。たまらないよね。」
天候の話はどこでも人のクチに簡単に上るものだ。
「そんなことをわざわざ言うことはないだろ。」
彼は怒りさえ感じた。
人は感じたことをなぜ安易にクチにしてしまうのか。
夏は暑いものだ。それでいいじゃないか。
俺はそんなに暑さを感じてはいないのだ。頼むから俺の感覚に影響を与えないで欲しい、彼は願った。
自分は暑く感じてなくても人の声を耳にしたとたん猛烈に汗をかいてしまった。
体がカッカとしてきてノボセたようになってしまうのだ。
考えないようにしても人々の声がアタマに入ってくる。そうして体が他人と同じことを感じるようになってしまう。
そうして体調がみるみる変わるのだ。
彼は眠れなくなった。
フラフラと深夜、彼はあてどなく街を歩いたりした。
どこか、精神を落ち着けねば。
何かの方法で気持ちを落ち着かせねば。でないと体がおかしくなる。
静かで、意識が干渉されないところにいなくては。
だが休まるところはなかった。どこでも人々の囁きが聞こえた。
やがて彼は人の声を聞くのが怖いほどになった。
あまり外出も出来なくなった。
買い物に出かける時は耳栓をするようになった。
夏は真っ盛り。
男は部屋を閉め切っていた。
人の声がどうしても聞こえてしまうからだ。
だから窓など開けられなかったのだ。
自然のままにしておいた方がいい、と、そんなことを彼は思った。
他人の声に影響を受けてしまうより感じたままでいられる方がいい。
暑さに身を委ねて自分が感じられるままにしていればいいのだ、と。
その方が落ち着けていい。それは自分の感覚なのだ。
太陽が出ていれば暑いのは当たり前だ。
夜になれば少しは涼しくなる。
クチに出して天気を呪う必要もない。
人に影響されるより自然のままでいられる方がずっと穏やかではないか、そう考えた彼は「暑さ対策」をしなくなった。
クーラーも持たず、扇風機さえ使わずに彼は部屋で過ごした。
人々が暑いと感じても俺には関係がない。体調が落ち着いていた方がいいのだ。
人々が暑いとかホコリっぽいとか考えたり話す。そんな他人の感覚から彼は自分を遠ざけようとしたのだった。
夏は暑いものとして過ごすのだ。
それだけじゃないか、彼はそう思った。
そうして彼はずっと汗だくで過ごした。
暑さの中、あまり眠れなくなった彼は閉め切った部屋でじっとしていた。
汗は吹き出るし頭もボウっとしていたかも知れない。それでも彼は感じるままにいたいと思った。
突然に人々の声が耳に入ってきて意識が影響を受け、体調がコロコロ変化することが困るのだ。
余計な雑音が怖い。
人の声を聞けばまた体調が狂わせられるのは目に見えているのだ。
「気候変動」なんて、天気が変わるのは当たり前じゃないか。
どんなに暑い部屋でもそんなにノボせたような感じはしない。
ダラダラと流れる汗はシャツが吸い取ってしまい、それが蒸発していた。
実際は体は冷えていたのだった。
「心頭滅却すれば火もまた涼し」
男はそんなことを言われて育ったことを思い出しハッとした。
意識は肉体の感覚に勝るのだ、と。
そして今の自分の状態を考えてゾッとした。
我慢が美徳であり耐えることが徳になると教えられたものだった。
そのうち、男は自分の汗を「寒い」と感じるようになった。
それは彼自身が感じた感覚だった。
激しくクシャミが出て鳥肌が立った。彼は戸惑った。
「これは自然じゃない。自分の意識のせいで体調が変わっているのだ。」
自分の意識で体の状態が変わってゆく気がして男は怖くなった。
暑さに対抗して意識が体を冷やしすぎている、そんな気がした。
自分の感覚がまた何かに奪われるのかと思い彼は怖くなった。
体には恒常性がある。
燃えるように暑い日、体温を一定に保とうとするのだ、と。そんな話がある。
男はそんな話を聞いたことがあった。
その話は彼に強い影響を与えた。
だから男は熱いものをクチにしてみた。体が冷えていたのだ。
この暑いのに茶漬けやトン汁、特に熱いモノを食べるようになった。
その方が食欲があった。
しかし冷えてゆく感覚は増すばかりだった。
男は体を温めねばならないと思った。
誰かの「暑いよ。」そんな声でも聞けばよかったのかも知れなかった。
彼はそんなことは思いもよらず、自分の体が冷えてゆく感覚に戸惑い、恐怖するばかりだった。
ある日のこと、男は息絶えているところを管理人によって発見された。
たいした家財道具のないアパートの一室で男は死んでいた。
死んだ男はひどく冷たかったという。
体を丸く抱えるようにして、まるで凍え死んだように見えたという。
死んだ体は冷たいものだ。
しかしそれ以上に男のカラダは冷たかった。
男の部屋には電気ストーブがあって恐ろしく暑い状態だった。
まさかストーブを点けていたのだろうか。
体が暑さに抗って自分を冷やそうとすることに彼は抵抗したのだった。
真夏というのに汗が蒸発して体が冷えてゆく感覚は誰にでもある。
それが彼を怖がらせた。
肉体の反応は男を冷やし続けた。
汗が蒸発し体温を奪った。
男はそこに恐怖したのだ。また精神が狂って体調がおかしくなっているのではないか、と。
気温と関わりなく体が制御不能な状態に陥っているのではないか、と。
男は錯乱していたのかも知れない。
ストーブを付け、締め切った部屋で体を温めていたのだ。
男はこの猛暑に凍死したようなものだった。
自分の意識による肉体反応のせいで。
「この暑さだから熱中症には注意って言われてたのに。」
「即身仏みたいだったって。」
人々が噂した。
「いや、きっと彼だけはひどく寒く感じていたのだ。」
「暑いだの寒いだの、あんまりクチにするのも考えものだよ。」
おしまい
※ あとがき
なんとかホラーっぽくなったかな?ww
暑い中、涼味をお届けしたいと思ったwww(笑)。 稲川某かよw。
「人間の方がどんな魔物より怖いだろう」、アタシはそんなタイプの人間。
まあ実際、アタシも似たようなものです。
扇風機当てて暮らしているわけです。
冷えてもいます。
やっぱり汗が蒸発すると肌がすごく冷たい。
スポーツ用のシャツなんて特に凍えますね。
ランニング用だか何かのピチピチのヤツ。
アレ、見た目がセクシーなんですが、すごく寒い。
猛暑じゃないととても着てられません。
だからたまには猛暑でもいいと思うアタシ。
暦の上ではもう秋だとか。
再び盛夏お見舞いを申し上げて。
どうぞご自愛ください。
おそまつ